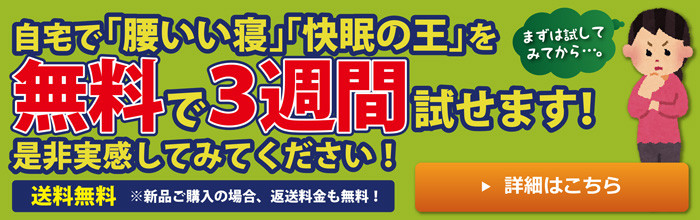目次
お手入れ方法を比較してマットレスを選ぼう
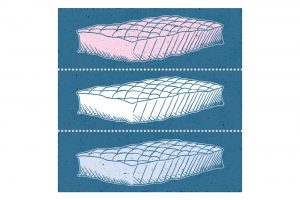
まずは人気メーカーのマットレスのお手入れ方法を表で見比べてみましょう。
| 商品名 | 丸洗い | 天日干し | 折りたたんでの 持ち運び |
|---|---|---|---|
| 腰いい寝 | クリーニング店で可 | 部屋干し推奨 | 3つ折可 |
| エアウィーヴ | 自宅で可 | 1時間程度まで | 3つ折可 |
| ムアツ布団 | 不可 | 1時間程度まで | 折りたたみ可 |
| テンピュール | 自宅で可 | 陰干し推奨 | 薄型のみ可 |
| マニ・スポーツ | 不可 | 陰干し推奨 | 一部のモデルのみ可 |
櫻道ふとん店の腰いい寝は自宅では丸洗いできませんが、クリーニング店でクリーニングできます。部屋干しを推奨しているので天日干しはしない方が無難です。3つ折りでたためるので持ち運びも楽でしょう。
エアウィーヴは、自宅で丸洗いできます。天日干しも可能ですが、1時間くらいまでにしておきましょう。3つ折りにして持ち運びもできます。
ムアツ布団はウレタンを使用しているため、丸洗いはできません。側生地を取り外せるタイプのものであれば、側生地のみ丸洗い可能です。天日干しは1時間くらいまでならできて、折りたたみもできます。
テンピュールは自宅で丸洗いできますが、陰干しを推奨しているため、天日干しはしない方がいいでしょう。薄型のマットレスのみ折りたためます。
マニ・スポーツは丸洗いできないため、濡れタオルで拭いたり消臭剤を使用してお手入れします。天日干しは推奨しておらず、陰干し推奨です。折りたためるモデルと折りたためないモデルがあります。
マットレスや敷布団お手入れしないとどうなる?

毎日睡眠を取っているマットレスや敷布団、ずっとお手入れをしないとどうなるのでしょうか。次に、お手入れをしないリスクについてみていきましょう。
マットレスのお手入れをしないリスクとは?
マットレスには、毎日の就寝時に汗や皮脂などの汚れがたまっていきます。
この汚れはそれ自体がお肌に反応してニキビなどができるだけでなく、ダニの餌となって、ダニの繁殖を助けてしまいます。ダニが繁殖しすぎると、アレルギーで咳やくしゃみ、鼻水が出るなど辛い思いをしてしまうのです。
また、夏場などは就寝中にかいた汗をマットレスが吸収します。これを放っておくと、マットレスの中に水分がたまり、カビが生える可能性もあります。
そこで、行いたいのがマットレスのクリーニングです。毎日マットレスを天日干しできれば、ダニを取り除くこともできるのですが、さすがに毎日お手入れをするのは難しいですよね。マットレスクリーニングであれば、プロの業者によって内部からしっかりと洗浄してもらえます。
普段、咳やたんが続いていて、もしかしてマットレスのダニが原因?と、思われる方は是非クリーニングを行いましょう。
正しいマットレスのお手入れ方法とは

それでは、マットレスをお手入れする際の正しい方法はどうすればよいのでしょうか、詳しくご説明します。
ダニ対策
まず、一番気になるのがマットレスに住み着いたダニの存在ですよね。一般的にダニ対策に行われているのが、布団用掃除機を使ってダニを吸い出すことです。とはいえ、布団用掃除機はまだまだ高価です。そこで、簡単に行えるのが、陰干しです。ダニは高温に弱いので、直射日光に当てるのも良い方法です。
しかし、商品にもよりますが、直射日光を受けることで品質が変わってしまうものがあります。そのため、基本的には物干しざおにマットレスをかけて陰干しをすると良いでしょう。頻度的には2週間から1週間に1度くらいが効果的です。
食べ物や飲み物をこぼしたとき
食べ物をこぼしたときは、マットレスの表面に、飲み物をこぼしたときは内部にまで染みわたってしまいます。汚れが表面的な物であれば、洗剤を付けたタオルで表面をポンポンと叩いて汚れを取っていきます。
汚れが内部にしみてしまった場合は、洗濯機を使って洗ってみましょう。ただし、素材や形状によっては洗濯できないものもあります。その場合は残念ですが、乾くまでカビが発生しやすくなります。陰干しして内部をしっかり乾燥させましょう。
マットレスは丸洗いできるのか?
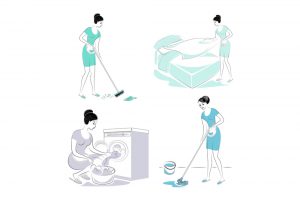
マットレスのお手入れをするときには、まずは種類や素材を確認する必要があります。側生地を取り外せるタイプのマットレスなら、取り外してマットレス本体とは別々に洗いましょう。
側生地というのは、最初からマットレスに付いている外側のカバーのことです。普段は取り外す機会がないため、取り外せるタイプのマットレスであっても、購入後一度も取り外したことがなく、取り外せることを知らないでいることもあります。
念のためマットレスの側面の端の方などを、じっくり見て確認してみましょう。
マットレス本体が洗濯機で洗えないタイプであっても、側生地だけは洗濯機で洗えます。側生地だけ洗濯機で通常通り洗い、マットレスはお風呂場で洗うのが無難です。
家庭用の洗濯機では、布団であれば洗濯可能ですが、マットレスはファミリータイプのかなり大きな洗濯機でも洗うのは難しいです。
小さめの布団タイプのマットレスであれば、洗濯機で洗える場合もあります。かなり大きな洗濯ネットに入れなければなりません。
縦方向に三つ折りにしてから、空気が入らないように丸めて洗濯ネットの中に入れます。布団に直接洗剤がかかってしまうとムラになる可能性があるため、あらかじめ水を洗濯機の中に入れて洗剤を溶かしておきましょう。
洗剤は粉タイプの洗剤よりも液体タイプの中性洗剤を使うのが望ましいです。粉タイプなら溶け出てしまう心配がありません。
自宅の洗濯機でマットレスを洗えるのは稀なケースであるため、自宅で洗うのであれば浴槽を使いましょう。ただ、折りたためるタイプのマットレスでないと、浴槽を使うやり方でも洗うのは難しいです。
洗濯機で洗うときと同じように、側生地を外せるタイプのマットレスであれば、外しておきます。
浴槽に40度くらいのお湯を張って洗濯用の洗剤を溶かしましょう。洗剤も洗濯機で洗う場合と同じく液体タイプの中性洗剤がおすすめです。
洗剤が均一に混ざったら、マットレス本体を浴槽に入れます。洗い方は主に手で押したり、足で軽く踏んだりして汚れを押し出すやり方です。
十分に汚れを押し出したら、浴槽の栓を抜いて水を流しましょう。そして今度は濯ぎです。再び浴槽に水を張って、洗ったときと同じように手で押したり、足で軽く踏んだりしてみましょう。2、3回程度濯ぎを繰り返すと、洗剤がほとんど流されて泡が出なくなります。
ウレタンやラテックス素材のマットレスの場合には、水に濡れると大きく劣化してしまうため、丸洗いしない方が無難です。
汚れた場合には、濡れタオルで拭くなどして対処しましょう。厚さが20センチ以上ある厚めのマットレスも自宅では洗わない方が無難です。ウレタンやラテックス素材と異なり、大きく劣化することはありませんが、乾かすのが非常に大変です。
マットレスを丸洗いした後の干し方

マットレスを丸洗いして濯ぎまで終わったら、次は干して乾かさなければなりません。ベランダや庭などで乾かすことになりますが、なるべく水分を抜いてから運びましょう。
十分に水分を抜いていないと、乾くのにかなり時間がかかってしまいます。また、水分を多く含んだ状態だと非常に重いです。ベランダや庭まで運び込む途中で水が垂れてしまうこともあるでしょう。
水を抜く際には、マットレスを踏むなどして抜こうとしても限界があります。そのため、浴槽の縁にかけておいて1時間程度放置しておくのがいいでしょう。
折りたたみ可能なマットレスなら、容易に浴槽の縁にかけられます。放置しておくと、自然と上から下に水が落ちてくるため、マットレスに含んでいる水もだいたい抜けます。
運び込もうとして、まだ水が垂れるようであれば、もう少し浴槽の縁にかけておくといいでしょう。
水を十分に抜いても、マットレスはかなり重いです。ベランダや庭に運ぶ途中で、何度か床に置くこともあるでしょう。
水を十分に抜いたつもりでも、まだ垂れてくることもあります。そのため、濡れたマットレスを運ぶ途中の通り道には、バスタオルなどを敷いておくのが望ましいです。
途中でいったんマットレスを下に置いても、水が垂れても床が汚れないで済みます。
マットレスを干すときに物干し竿が1本だと重さに耐えきれない可能性が高いです。マットレスはただでさえ重く、水を含んでいるのでさらに重さが増しています。また、重さには耐え切れても、1本だとバランスもあまりよくありません。
そのため、2本の物干し竿にかけて干すと安全です。日光がよく当たる場所に干すよりは、風通しの良い場所で陰干しすると劣化もしにくいでしょう。2本の物干し竿の間を開けておくと、風通しも良くなるので乾きやすいです。
マットレスは乾くのに非常に時間がかかりますが、完全に乾くまで干しておきましょう。中途半端に乾いた状態で使ってしまうと、臭くなってしまうことがあります。
マットレスの厚さや素材にもよりますが1日だけでは足りないことが多いです。マットレスを洗ってお手入れするときには、乾くまでの間に使う代わりの寝具も用意しておく必要があります。
マットレスをクリーニングしてくれる業者はある?

マットレスをお手入れしたくても、浴槽が狭いなどの理由で、自宅でやるのは難しいケースもあるでしょう。洗うことはできそうでも、干す場所がないというケースも少なくありません。
マットレスはかなり大きいため、普段洗濯物を干しているスペースに干せないことも多いです。
自宅でお手入れできない状況で、長年使用しているマットレスが汚れていそうだと感じたら、業者にクリーニングを依頼する方法もあります。
ただし、通常のクリーニング店に依頼するのではありません。通常のクリーニング店では断られてしまうことが多いです。
マットレス専門のクリーニング業者があります。通常のクリーニング店のように、店舗に持ち込んで預かってもらう形ではなく、スタッフが自宅まで出張してきてくれて、自宅でクリーニング作業を行う業者がほとんどです。
マットレスクリーニングの費用相場はかなり高めで、シングルの片面だけの場合で8,000円から15,000円くらいかかります。セミダブルだと、シングルサイズよりも2,000円程度高く、ダブルならセミダブルよりもさらに2,000円程度高いです。
両面のクリーニングを依頼するのであれば、1.5倍から2倍くらいの料金になります。ただ、片面だけだと内部にダニが住みついている場合でも、十分に除去できません。クリーニングを依頼するなら、なるべく両面にしておくのがおすすめです。
また、マットレス専門のクリーニング業者であっても、全てのマットレスをクリーニングできるわけではありません。
素材によっては断られてしまうこともあります。主にウレタンやラテックス素材のマットレスは水に濡れると大きく劣化してしまうため、断られやすいです。ただ、高反発ウレタンであれば、対応してくれる業者も稀にあります。
依頼するときには、まずマットレスの素材を確認した上で、対応可能な業者をいくつかピックアップしておきましょう。
見積もりをとってもらい、料金やクリーニング内容、日程などを考慮した上で、依頼先を決めるという流れです。複数の業者から見積もりをとってもらうことで、高すぎる業者に当たるのを避けられます。
当日に業者が自宅に来たら、最初に作業内容や時間などについて説明してくれます。作業はゴミの吸引から始めて、次にスチーム洗浄、アルカリ電解水・バキューム洗浄という流れで行う業者が多いです。最後に専用のドライヤーを使って乾燥させて終了です。
ゴミの吸引で15分程度、スチーム洗浄とアルカリ電解水・バキューム洗浄でそれぞれ25分程度かかるため、洗浄作業にかかる時間は1時間を少し超えるくらいでしょう。
乾燥させるのには、洗浄作業と同じくらいかもう少し長いくらいの時間がかかります。トータルで2時間半くらいかかると捉えておくといいでしょう。
マットレスが臭い!?簡単に脱臭できるお手入れ

マットレスをクリーニングするほどでなくても、汗臭い臭いが気になって手入れしたいときがあるでしょう。消臭剤を使うと、少し汗臭い程度の臭いなら消えることが多いです。
なるべく小まめに消臭剤を使うようにしていれば、快適な環境を保てるでしょう。消臭剤なら手軽に使えるので手間もほとんどかかりません。
消臭剤を使用しても、臭いの元が絶たれるわけではないため、次の日になると再び臭くなることがあります。
臭いの元を絶つには消臭剤に加えて天日干しすると効果的です。雑菌がある程度死滅するので脱臭効果がアップします。
消臭スプレーは市販のものを使う人が多いですが、自分で作ることも可能です。アルコールと水、アロマオイル、クエン酸を混ぜてクエン酸系の消臭スプレーが作れます。
アルコールは10パーセント程度に薄めて使用するため、安い甲類焼酎で大丈夫です。アルコールにクエン酸を大さじ胃1杯入れてかき混ぜてから水で薄めて10パーセント前後の濃度にします。最後にアロマオイルを1滴加えれば完成です。
ワイドハイターなど、洗濯機で使用する液体酸素系漂白剤を薄めるだけでも、消臭スプレーを作れます。洗濯をするときに使用する濃度の2倍くらいの濃度にするとちょうどいいです。
米のとぎ汁に砂糖と塩を混ぜて作る消臭スプレーもあります。450ミリリットルのとぎ汁に、砂糖15グラムと塩5グラムを加えましょう。
よくかき混ぜてペットボトルの中に入れて常温で1週間ほど放置してから、10倍から50倍程度に薄めて使用します。市販の消臭スプレーを使う場合と比べてだいぶ安く済みます。
普段からするお手入れ
日常的に時間を取れるなら、断然、天日干しがおすすめです。ダニ退治にもなりますし、マットレス内部の湿気も取ることができます。ただ、商品によっては、天日干しができないため、説明書をよく読んでから行いましょう。
お手入れが簡単にできるマットレスの選び方
マットレスを清潔に使いたいのであれば、必ずお手入れが必要になってきます。ただ、毎日お手入れをするとなると忙しくてそんな時間がないなんてことも。そこで、お手入れが簡単にできるマットレスの選び方をまとめました。
まず、チェックしたいのが雑菌が繁殖しにくいマットレスです。最近では、特殊な化学繊維を使って雑菌が繁殖しにくくなるマットレスが開発されています。雑菌が繁殖しにくいとお手入れする回数も減るので、楽になります。
マットレスのお手入れしやすい素材から選ぶ方法とは
また、マットレスの素材もチェックしましょう。現在、お手入れの簡単さで注目されているのが、羊毛です。
羊毛は吸湿性に優れているだけでなく、放湿性にも優れています。そのため、眠ったところで、湿気がたまりにくく、雑菌も繁殖しにくいとされています。実際のお手入れ時間も月に1回ほど干すだけで済みます。
逆に、お手入れのしにくさで選ぶと低反発マットレスは良くありません。低反発マットレスは、弾力性が弱い反面、ウレタンの密度が高くなっています。
そのため、天日干しをしようと思っても重さがあるため持ち運びにくくなっています。また、一度洗濯をしてしまうとなかなか乾かないと言うデメリットもそろいます。
これとは反対に、高反発マットレスは、通気性も良くお手入れがしやすいのが魅力的です。商品によっては、速乾性に優れていて丸ごと洗濯機で洗うことができるものもあります。
これからマットレスや敷き布団を購入する際は、
・丸洗いは可能なのか?
・自分で干すことができるのか
・折り畳んでの持ち運びは可能か
というように、ご自身の生活と合わせてみて、自分にとってお手入れがしやすいマットレスや敷き布団を選ぶようにするとよいでしょう。きっと良質な睡眠をとることができますよ。